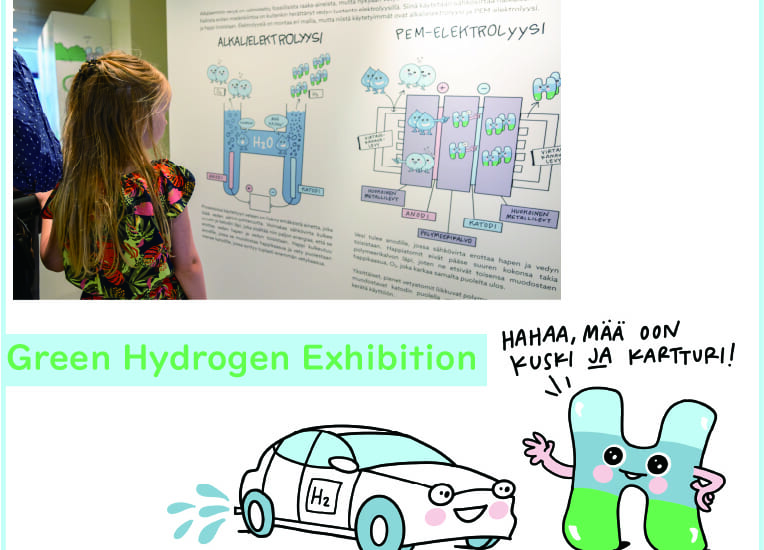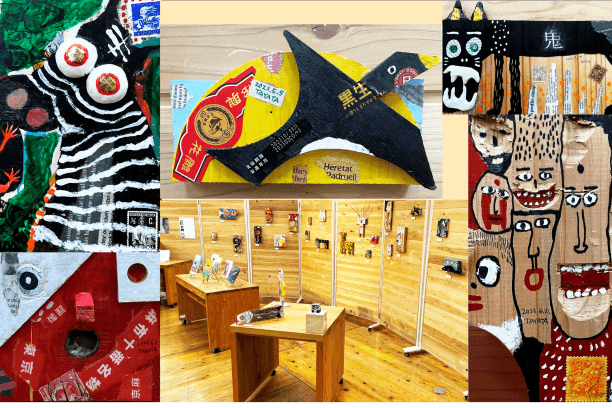- レクチャー
- フィールドワーク
- 子ども
- 大人
- 生物多様性
- 抽選
【終了しました】見て、感じて、聞いて学ぼうキノコのこと

※本講座は、講師保坂健太郎氏の体調不良のため、坂井きのこ氏のみで実施します。尚、午後のレクチャーは中止といたします。
2025年6月28日(土)実施
観察会では浜離宮恩賜庭園でキノコの観察を行います。自然豊かな園内では、四季折々のキノコが生える様子を見ることができます。それぞれの特徴や周りの環境との関係などの解説を受けながら、都会における生物多様性について、キノコに焦点を当てて学びます。芝生や木の根元、落ち葉などから、どのようなキノコが生えているか皆さんで見つけてみましょう。
レクチャーでは、数億年前からキノコが環境と深く関わりながら生息していることや、一生に一度は見てみたいキノコ、日常のキノコあるあるまで、国立科学博物館植物研究部菌類・藻類研究グループ研究主幹であり、キノコの研究を続ける保坂健太郎氏と、キノコの魅力を日々発信するきのこ大好き芸人、坂井きのこ氏という違った立場のお二人の講師から、驚きと魅力にあふれたキノコのお話の数々をうかがいます。
お二人が初めて揃う貴重な機会に是非お越しください。
※荒天時は港区立エコプラザで、キノコの生態や驚きの働きなどについて学びます。(10:00~11:30)
| 日時 | 2025年6月28日(土)10:00~15:00(受付は9:45~)※12:00~13:30昼休憩 |
| 会場 | 午前:浜離宮恩賜庭園(現地集合) 午後:港区立エコプラザ ※詳細は参加案内にてお知らせします。 |
| 対象 | 港区在住・在勤・在学を中心とした小学4年生以上の方(小学生は保護者同伴) ※区外の方も参加できます |
| 講師 | 保坂 健太郎氏(独立行政法人国立科学博物館 植物研究部 研究主幹) 【プロフィール】 国立科学博物館植物研究部菌類・藻類研究グループ、研究主幹。 沖縄県の琉球大学生物学科で卒業研究にきのこを選んで以来、きのこの研究をつづける。 アメリカのオレゴン州立大学で博士号取得。シカゴのフィールド博物館でのポスドク生活を経て2008年より現職。 地球上の全ての大陸できのこ調査をするのが夢だが、残るは南極大陸だけなので、次は深海か空か宇宙か、と妄想を膨らませている。専門書から図鑑、絵本、漫画まで広く監修。主な著書に『きのこの不思議(誠文堂新光社)』『小学館の図鑑NEO きのこ』など。 坂井 きのこ氏(きのこ大好き芸人)  【プロフィール】 3歳の頃からキノコに魅了され、今では800種類を熟知。365日キノコを食べて、自宅では何種類ものキノコを栽培している芸能界一のキノコフリーク。現在ではキノコの素晴らしさを広める為にSNSやテレビ、ラジオ、講演会などで活動中。 |
| 定員 | 20名(抽選) |
| 参加費 | 無料 |
| 持ち物 | 水分補給用の飲み物 |
| 服装 | 歩きやすい靴、服装、帽子(日傘の利用はご遠慮ください)、雨天時はレインコート |
【当日の様子】
最初に、芝生ゾーンでクロハツを発見しました。数メートル離れた所に生えているクロマツと根の部分でつながって共生していると説明がありました。菌類には木とお互いに栄養や酸素をやり取りして共生する菌根菌と、枯れた植物や動物の死骸などを分解して栄養を吸収する腐生菌があります。植物の主要成分であるセルロースやリグニンを分解できるのは菌類のみであるため、物質循環システムにキノコは必要不可欠とのことです。
その後園内の比較的木が生い茂っていて土壌が豊かな場所を歩き、ナラタケモドキ、ケガワタケ、カワキタケ、スエヒロタケ、チャホウキタケ、アラゲキクラゲなど約15種類のキノコを観察したり手触りを確かめたりすることができました。スミレホコリタケは胞子がほぼ散った後でしたが、柄(え)の部分を握ると残った胞子が飛び散る様子を確認できました。胞子を飛ばすためにキノコは虫や雨の力などを使いますが、ホコリタケの仲間は、傘の部分が大きく球体に膨れた後、はじけることで胞子を飛ばします。
その他、キノコは土の中に張り巡らせている菌糸に、人間の「言語」に似た構造の電気信号を送り、栄養源などの情報をやり取りしていることが確認されたというキノコの新しい研究結果が紹介されました。
参加者からは、「実際に自生しているきのこを見て回れる貴重な体験でした」「菌類が土の中でどのような活動をしているのか知ることができた。同定の方法や最新の研究の内容が興味深かった」などの感想がありました。
多種多様なキノコが身近に存在し、生態系にとって重要な働きをしていることや、生存戦略について知る機会になりました。
※浜離宮恩賜庭園より特別な許可を得て、観察のために必要な場合に限り、講師のみがキノコを採取しています。(持ち帰りはしていません)
通常はキノコを含め、草・花・石など園内にあるものの採取、持ち帰りは禁止されています。